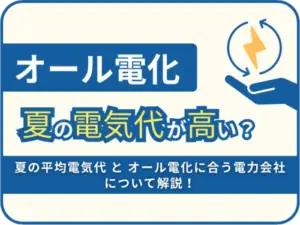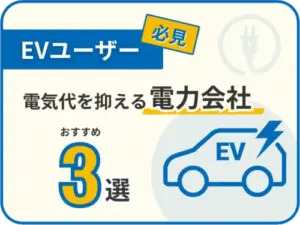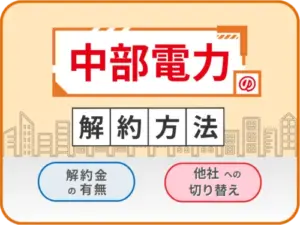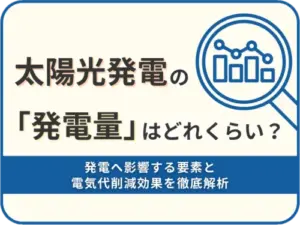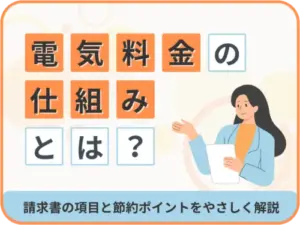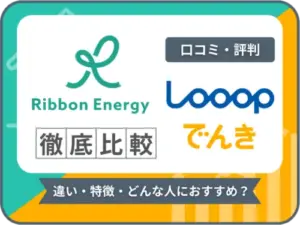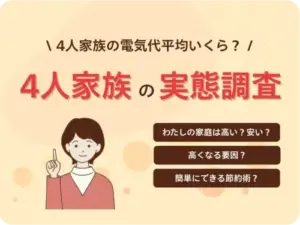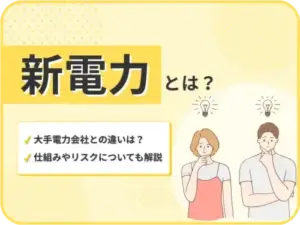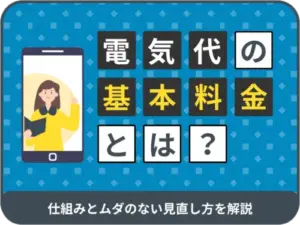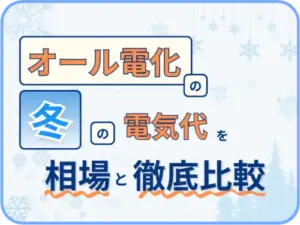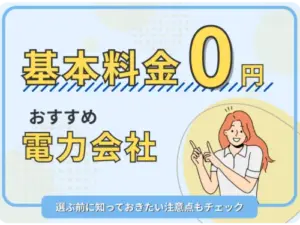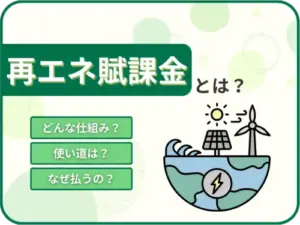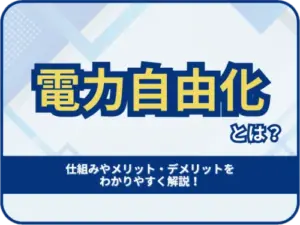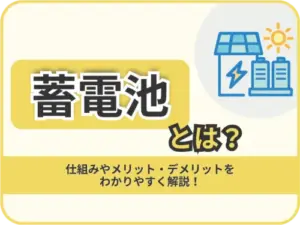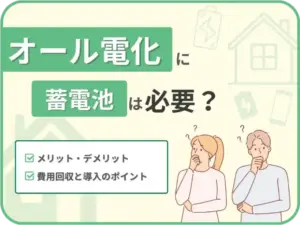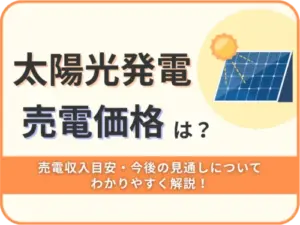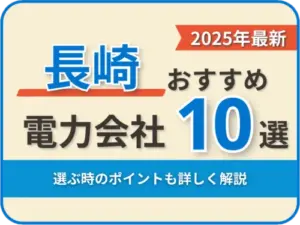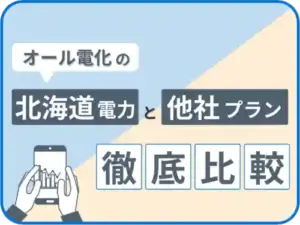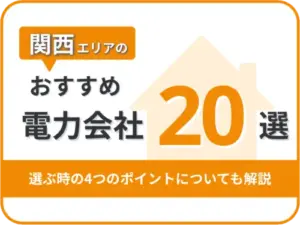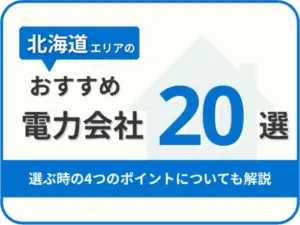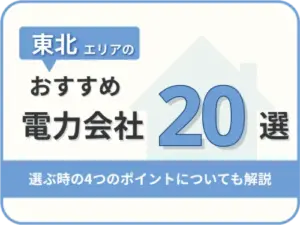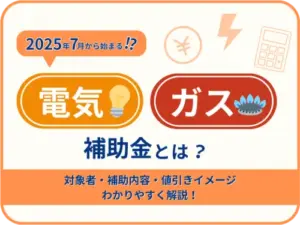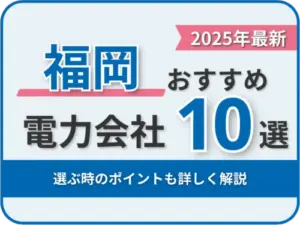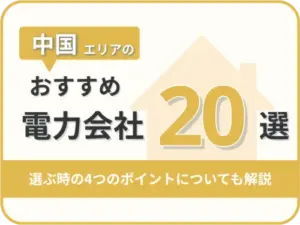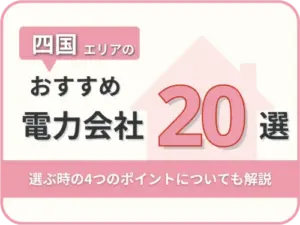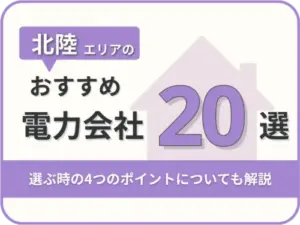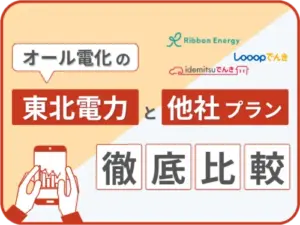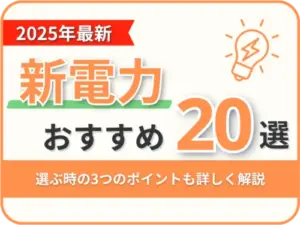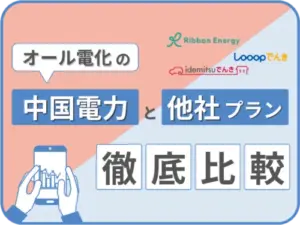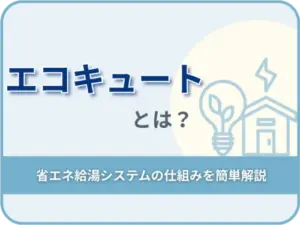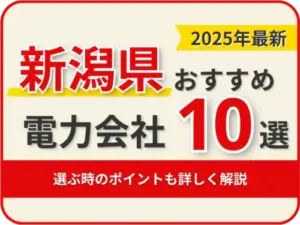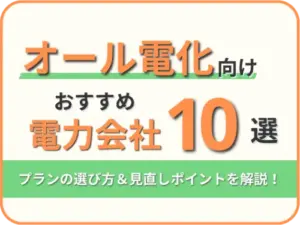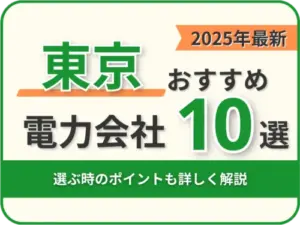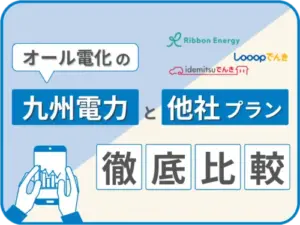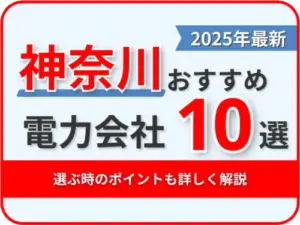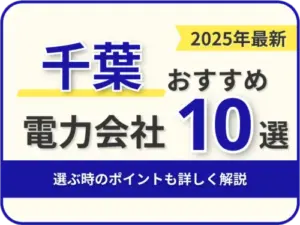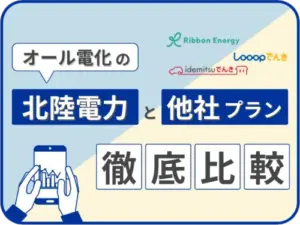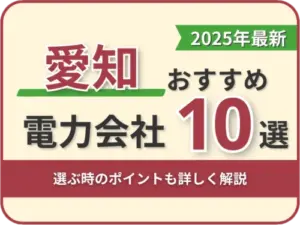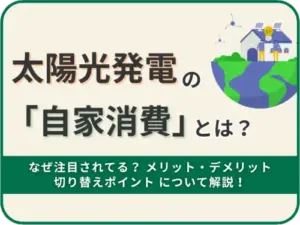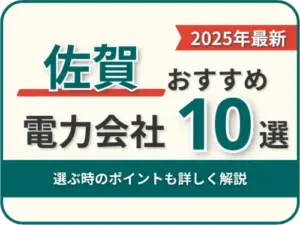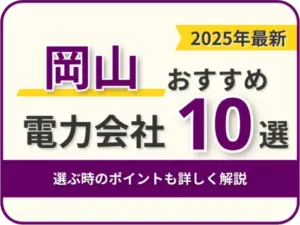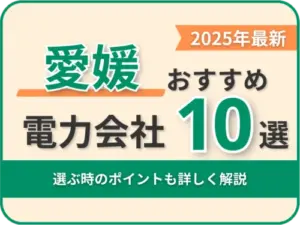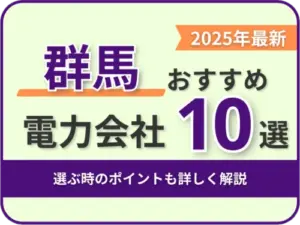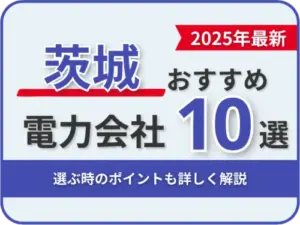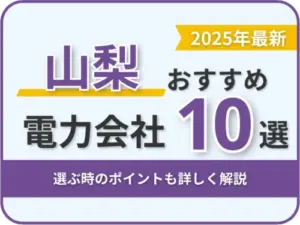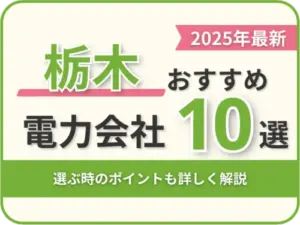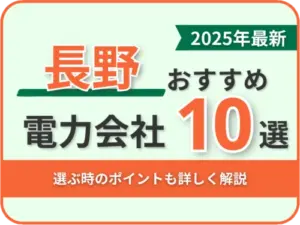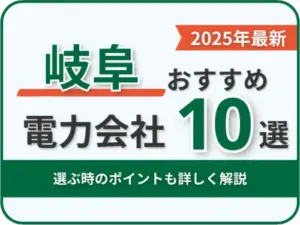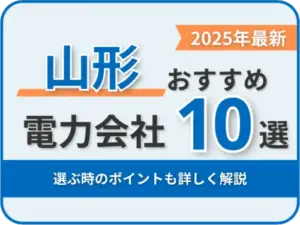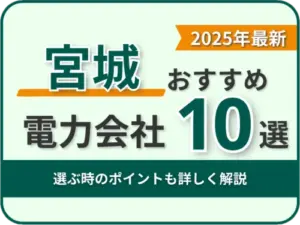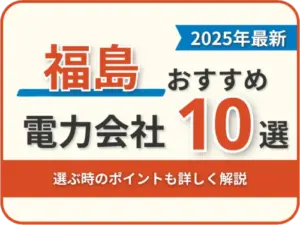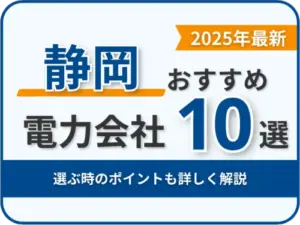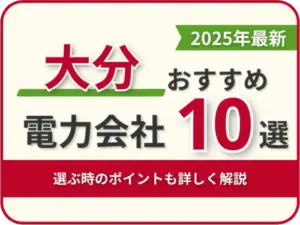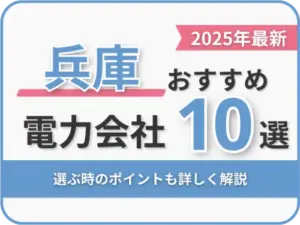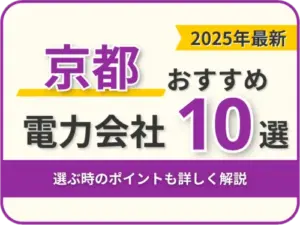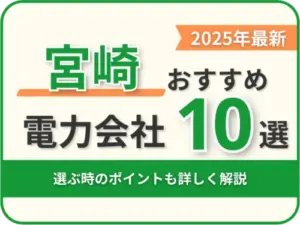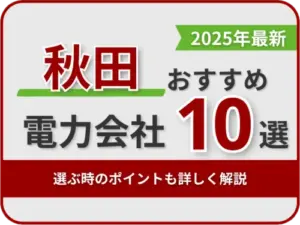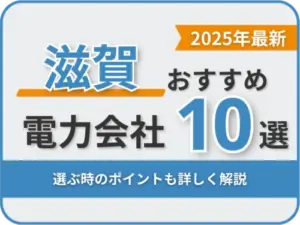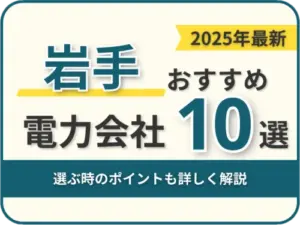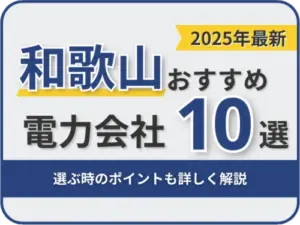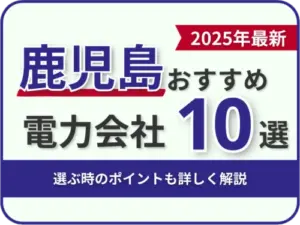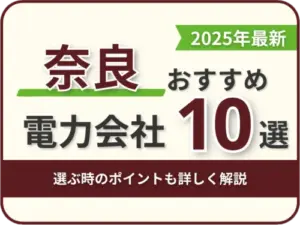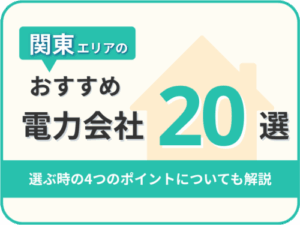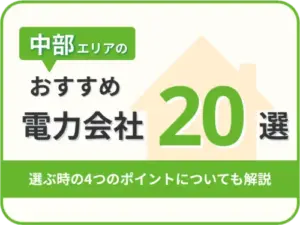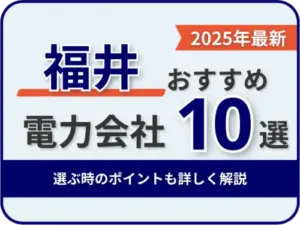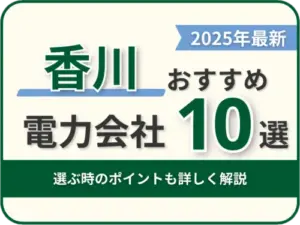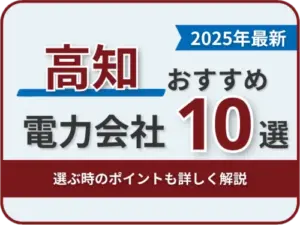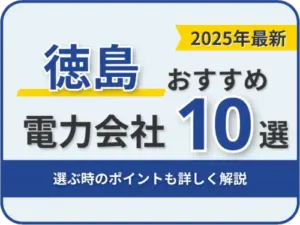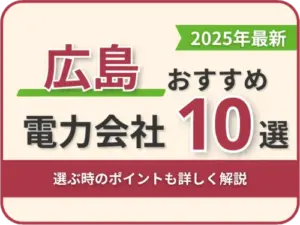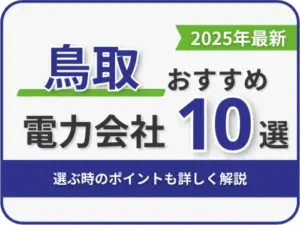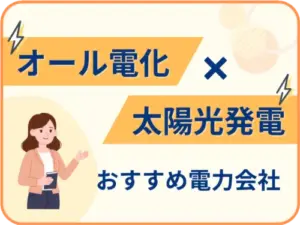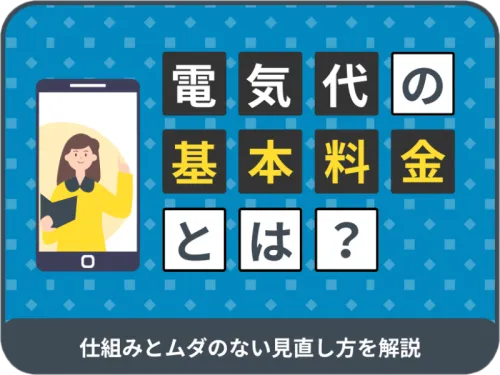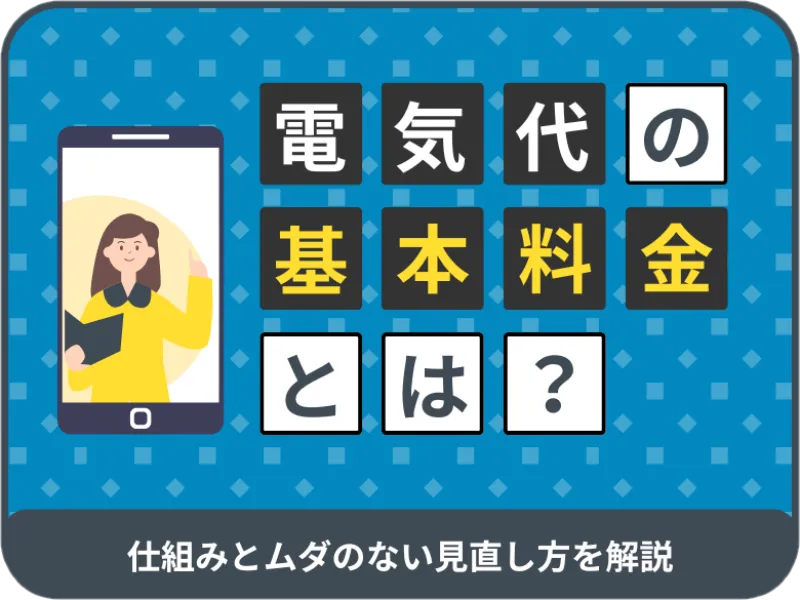
電気代の明細を見ていると、
「基本料金って何だろう?」と疑問に思ったことはありませんか?
電気を使った分だけ払っていると思いきや、毎月しっかりと請求される基本料金でも、
・そもそも何のためにかかっているのか
・どうやって金額が決まるのか
・もっと安くできる方法はあるのか
実はよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな「電気代の基本料金」について、仕組みから計算方法、見直しのヒントまでわかりやすく解説します。
しっかり理解することで、毎月の電気代の中身がスッキリと見えてきますよ!
【まずはここから】電気代の「基本料金」とは?

まずは、電気代における「基本料金」ってそもそも何なのかを整理しましょう!
「毎月決まってかかる料金」とはなんとなく知っていても、実際にはどのような仕組みで設定されているのかまでは、意外と知られていません。
ここでは、電気代の構成要素を確認しながら、基本料金の役割と成り立ちについてわかりやすく解説すていきます!
電気代の内訳:基本料金と電力量料金の違い
電気代は、「使った分だけ払う」と思われがちですが、実際は少し違います。
基本料金・電力量料金・調整費用という3つの要素で構成されています。
まずはそれぞれの役割を理解しましょう。
【電気代の3つの構成要素】
- 基本料金:契約している容量(アンペア数)に応じた毎月固定でかかる費用
- 電力量料金:実際に使用した電力量(kWh)に応じた費用
- 調整費(燃料費調整額・電源調達調整費):燃料価格変動や市場価格変動のための費用
このうち「基本料金」と「電力量料金」が電気代の中心で、そこに調整費が加わります。
【具体例】
例えば、ある家族が
契約容量:30A(基本料金 935円)
月間使用量:300kWh
電力量単価:~120kWh:29.80円・121~300kWh:36.40円
だった場合
電力量料金:120kWh×29.80円=3,576円・180kWh×36.40円=6,552円
合計電気代:基本料金:935円+電力量料金:10,128円=11,063(+燃料調整費)
引用:東京電力エナジーパートナー|スタンダードプランをもとに計算
電気代=固定+従量+調整の3つで構成されることをまず押さえておきましょう。
基本料金が発生する理由:送配電網の維持費とは
「電気をまったく使っていない月でも基本料金が発生するのはなぜ?」
それは、電力会社が常に電気を供給できる状態を維持しているためです。具体的な費用構造を見てみましょう。
【基本料金がカバーする主な費用】
- 電気を家まで届けるための電線や設備を整備・維持する費用
- 24時間いつでも電気が使えるようにするための準備費用
- 台風や地震などのトラブルが起きたときに、すぐ復旧できるための備え
- 電気を安定して送り続けるために働く人たちの人件費
つまり、電気を使う・使わないにかかわらず、「必要なときにいつでも電気を使える」状態を守るためのコストが、基本料金として請求されているのです。
基本料金は、生活に欠かせない「電気の安心」を支えるための料金なんですね。
基本料金の計算方法:契約アンペア数と金額の関係
基本料金は、契約しているアンペア数(容量)によって決まります。
契約アンペア数とは、家庭で同時に使える電気の量(電流の最大値)のこと。
このアンペア数が大きいほど、たくさんの家電を同時に動かすことができる反面、基本料金も高くなる仕組みです。
たとえば、大きな冷蔵庫やエアコンを複数台同時に動かす家庭やオール電化世帯では、契約アンペア数も大きく設定されているケースが多くなります。
【基本料金が決まる仕組み】
- 契約しているアンペア数に応じて、毎月の基本料金が設定される
- アンペア数が大きいほど、準備すべき電気の量が増えるため、料金も高くなる
| 契約アンペア数 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 10A | 311.75円 |
| 15A | 467.63円 |
| 20A | 623.5円 |
| 30A | 935.25円 |
| 40A | 1247円 |
| 50A | 1558.75円 |
| 60A | 1870.5円 |
- 「契約アンペア数 × 単価」で基本料金が決まる
- アンペア数は暮らし方に合わせて見直すことができる
適切なアンペア数を選ぶことで、無駄な基本料金をカットできるかもしれません。
関連記事必見!契約アンペア変更で年間電気代を劇的削減
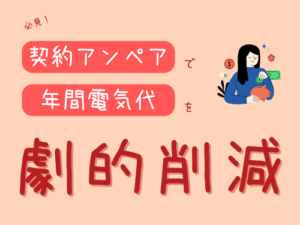
うちに合うのは何アンペア?家族別オール電化の目安とは?

契約電力(契約容量)の影響:なぜアンペア数で決まるのか?
契約電力(契約容量)は、電気代の基本料金に直接影響を与える大事なポイントです。
基本料金がアンペア数によって決まる仕組みを理解すれば、自分にとって無駄のない適切な契約容量を選ぶ手助けになるかと思います。
このパートでは、
- なぜ契約容量が基本料金に関係するのか
- 生活スタイルに合った契約容量の選び方
- 契約容量が増減する要因について、わかりやすく整理していきます。
【契約容量と基本料金の関係】
- 契約アンペア数が大きいほど、電力会社は「同時使用」に備える必要がある
- そのため、発電所や電線などの設備規模が大きくなり、維持費が増加
- 結果として、契約容量に応じた基本料金が高く設定される仕組み
【契約容量の選び方と調整方法】
- 小さすぎる契約容量
→ ブレーカーが頻繁に落ちるなど、生活に支障が出るリスク - 大きすぎる契約容量
→ 実際に必要な容量よりも高い基本料金を無駄に支払ってしまう
生活スタイルに合わせて、必要最小限の契約容量に設定するのが理想です!
【チェックポイント例】
- 家族構成(単身世帯/ファミリー世帯)
- 同時に使う家電の数(エアコン、IHクッキングヒーター、エコキュートなど)
- 在宅時間や生活パターン(昼間・夜間どちら中心か)
【契約容量が変わる要因】
- 家族の人数が増えた・減った
- 生活スタイルの変化(在宅勤務、子どもの独立など)
- 新しい大型家電の購入(例:エコキュート、業務用エアコン)
生活の変化に応じて、契約容量の見直しも考えるといいでしょう。
契約容量は「自分たちの暮らしに本当に必要な電気量」を基準に選ぶことが大切です。
適切な契約設定が、基本料金の無駄を減らす第一歩になります!
【実際いくら?】契約アンペア別・電気代の基本料金相場

ここまでで、基本料金の仕組みや契約容量の影響について理解できたと思います。
では実際に、契約しているアンペア数によって毎月どれくらいの基本料金がかかるのかを見てみましょう!
ここでは、代表的な電力会社の料金例をもとに、契約アンペア数別の基本料金相場をわかりやすく紹介します。自分の契約内容と照らし合わせながら、参考にしてみてください。
契約アンペアごとの基本料金一覧(東京電力の場合)
契約アンペア数が変わると、基本料金も大きく変わります。
まずは、東京電力エナジーパートナーの標準プラン(従量電灯B)の料金例を見てみましょう。
| 契約アンペア数 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 10A | 311.75円 |
| 15A | 467.63円 |
| 20A | 623.5円 |
| 30A | 935.25円 |
| 40A | 1247円 |
| 50A | 1558.75円 |
| 60A | 1870.5円 |
ポイント
- 10A刻みで契約容量を上げるたびに、基本料金も段階的に増える
- 生活スタイルに対して過剰なアンペア契約をしていると無駄な出費につながる
- 逆に、契約容量が足りないとブレーカーが落ちるリスクもある
→ 「今の生活に本当に必要な容量か?」を一度見直すことが大切です。
他エリア(関西・中部など)との違い:なぜ地域で異なる?
実は、電気の基本料金は地域によって異なります。
これは、エリアごとの送配電網の整備状況や、契約体系の違いが背景にあります。
【地域ごとの違いポイント】
- 関東(東京電力)や北海道(北海道電力)ではアンペア契約が主流
- 関西(関西電力)や中部(中部電力)では、アンペア契約がない(基本料金は一律型)
- 地域によって電気の使われ方(冷暖房需要など)が異なるため、料金体系も最適化されている
| 内容 | 基本料金 |
|---|---|
| 最低料金制(15kWhまで) | 522.58円 |
引用:関西電力|従量電灯A
関西では基本料金が「最低料金制」になっており、実際の使い方に応じて変動します。
地域によって「契約方法」と「基本料金の考え方」自体が違うので、引っ越し時などは特に注意しましょう。
最低料金制とは?基本料金との違いと適用されるケース
電気代の料金体系には、「基本料金制」と「最低料金制」という2つの考え方があります。
どちらも電気を使わなくても支払う固定費という点では共通していますが、料金が決まる基準や、追加課金の仕組みに違いがあります。
ここでは、両者の違いをわかりやすく整理していきます。
| 比較項目 | 基本料金制 | 最低料金制 |
|---|---|---|
| 料金の決まり方 | 契約容量(アンペア数)に応じた固定料金 | 一定の使用量までは最低料金、それを超えた分に従量料金がかかる |
| 支払いの発生 | 使わなくても契約容量に応じた基本料金が発生する | 使わなくても最低料金が発生する |
| 特徴 | 基本料金は常に固定(使っても使わなくても変わらない) | 基準(例:15kWh)を超えた分だけ料金が追加される |
最低料金制の仕組みをもう少し詳しく
最低料金制では、電気の使用量が少ない場合でも、あらかじめ決められた一定量(例:15kWh)までは定額の料金がかかる仕組みです。
そしてその基準を超えた分だけ、使った分に応じた料金が追加で発生する形になっています。
参考:関西電力「従量電灯A」プランの最低料金制
| 内容 | 最低料金 |
|---|---|
| 最低料金制(15kWhまで) | 522.58円 |
| 15kWhを超えた分 | 電力量料金(1段階〜)が追加で発生 |
引用:関西電力|従量電灯A
まとめ
最低料金制は、「使った分すべてに料金がかかる」わけではなく、一定量までは定額でカバーされる仕組みです。
その基準を超えた分だけ、追加で電力量料金が発生するため、「最低料金と使用量で二重にかかる」というわけではありません。
【ムダをなくす】自宅の基本料金が高いかチェックする方法
「もしかして、うちの基本料金って高すぎるのでは…?」そう感じたことはありませんか?
基本料金は、契約しているアンペア数に応じて毎月固定で発生します。もし今の暮らしに対して契約容量が過剰なら、無駄な基本料金を払っている可能性も。
ここでは、
- まず自宅の契約内容を確認する方法
- 現状が自分に合っているか判断するポイント
わかりやすく整理していきます。
電気料金明細のどこを見る?基本料金確認のポイント
まずは、毎月届く電気料金明細書を見てみましょう。ここに、契約アンペア数と基本料金の情報が記載されています。
【明細書でチェックするポイント】
・「契約アンペア数」または「契約容量」欄
→ 例:30A、40Aなどと書かれている
・「基本料金」欄
→ 毎月固定で支払っている金額が表示されている
・「電力量料金」とのバランス
→ 使用量が少ないのに基本料金が高い場合は見直し対象
契約アンペア数と基本料金が、今の生活に見合っているか意識して見るのがポイントです。
生活スタイルと契約容量のバランスを考える(家電と負荷の例)
自分の契約アンペア数がわかったら、今の生活スタイルに本当に必要な容量かを見直してみましょう。
【契約容量の目安例】
・単身世帯(エアコン1台・電子レンジ・冷蔵庫など)
→ 20A〜30Aで十分な場合も
・ファミリー世帯(複数エアコン・IHクッキングヒーター・洗濯乾燥機あり)
→ 40A〜50Aが必要なケースも
・高齢者世帯(電気使用が少ない)
→ 20A程度でも問題ないことも
【チェックする家電の例】
冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・ドライヤーなど、瞬間的に電力を多く消費する家電を同時に何台動かすことが多いか
→ブレーカーが頻繁に落ちない範囲で、できるだけコンパクトな契約容量に見直すとムダがないです。
- 毎月の明細書・ブレーカー・契約書で契約容量をチェック
- 生活スタイルに対して容量が大きすぎないか見直す
- 必要に応じて、アンペア数の変更を検討するのが賢い節約法
【料金体系の違い】基本料金0円プランの仕組みを理解しよう

基本料金0円プランは、毎月の固定費(基本料金)をゼロにする代わりに、電気を使った量に応じて必要な費用を支払う仕組みになっています。
たとえば、普段は基本料金の中に含まれている「電気を家まで届けるための仕組み(電線や設備)」の維持費など基本料金でカバーしていた様々な必要コストを、0円プランでは使った分の電気代に上乗せされる形で回収されます。
【具体的な仕組み】
- 毎月の基本料金はゼロ
- そのかわり、電気を使った量に応じて、インフラ維持にかかる費用も負担する
- 使った分だけ支払うので、たくさん使うと支払額が増える
【イメージ】
- 電気をあまり使わない月 → 支払いはほぼゼロに近い
- 電気をたくさん使った月 → インフラ維持費も含めて、支払いが大きくなる
→ 基本料金0円プランは、「使わなければ安い」が、「使った分だけコストも増える」仕組みです。
【メリット】
・使わない月は本当に安くなる(ほぼゼロ円も可能)
・いままで固定で払っていた設備維持のコストが、使った分だけになる
・節電意識が高い人には、実際の使用量に応じた公平な設計
【デメリット】
・電気をたくさん使う月は、支払いが大きく跳ねやすい
・電気の使い方によっては、従来の基本料金制より高くなるリスクも
・契約前に、単価や料金設定をしっかり確認しないと損をする可能性がある
「0円だから安い」ではなく、「どういう仕組みで安くなるのか」を理解することが大切。
使う量に応じてコストが動く=生活スタイルによって向き不向きがあるプランです。
基本料金0円プランを選ぶときに注意すべきポイント
「基本料金が0円なら、どこの電力会社を選んでもお得なんじゃない?」
そう思ってしまいがちですが、電力会社ごとに条件や仕組みは少しずつ違います。
契約前に以下のポイントを確認しておくことで、「思ったより高くなった…」という後悔を防ぐことができます。
電力量単価が割高になっていないか
基本料金が0円でも、1kWhあたりの電力量料金が高めに設定されていることがあります。
その場合、電気をたくさん使うと、結果的にトータルの電気代が高くなることに。
たとえば:
- 従来のプランでは1kWhあたり27円程度
- 基本料金0円プランでは30円以上に設定されていることも珍しくない
→ 使えば使うほど、その差が積み重なって支払い総額が膨らむ点に注意が必要です。
調整費(燃料費調整額、電源調達調整費)が高めに設定されていないか
電気料金には、発電や仕入れにかかるコストの変動を反映する「調整費」があります。
この調整費は、単価が電力会社ごとに異なり、しかも毎月変動するため、見えにくいけれど大きな差が生まれるポイントです。
【注意点】
表面上の「基本料金0円」や「電力量単価」が安く見えても、実際には調整費で数千円以上上乗せされることも。
契約前に「今月の調整費単価」や「料金表の備考欄」などを確認しておくと安心です。
電源調達調整費の正体とは?電気代が高いのはなぜ?

今日からできる!燃料費調整額に負けない賢い電気の使い方ガイド

契約に特別な条件や期間が設けられていないか
基本料金0円プランには、以下のような前提条件や制限がついていることがあります:
- 12ヶ月間だけ基本料金0円、その後は有料になる
- ガスや別サービスとセット契約が前提になっている
- 「1ヶ月目だけ割引」など、キャンペーンが一時的な場合もある
→ こうした条件は、申込みページの下部や注意書きに小さく書かれていることが多いため、契約前に必ず目を通しておきましょう。
「基本料金0円」でも、他の部分で料金が上乗せされていないかを確認することが重要です。
特に、「電力量単価」「調整費(燃料費調整額、電源調達調整費)」「契約条件」の3点は、契約前に必ずチェックしておきましょう。
【まとめ】基本料金の仕組みを理解して、電気代のムダをなくそう
ここまで見てきたように、電気代の中でも見落としがちな「基本料金」は、実は家庭の電気代を左右する重要なポイントです。
「使っていなくてもかかるお金」である一方で、プランの選び方によっては必要以上に払ってしまっているケースも少なくありません。
電気代を見直す第一歩は、自分の契約内容(契約容量・料金プラン)を知ること、そして「基本料金がどう決まっていて、どう負担しているのか」を正しく理解することです。
基本料金があるプラン、ないプラン、それぞれにメリット・デメリットがありますが、仕組みさえ理解しておけば、無理なく自分に合った選択ができるはずです。
まとめポイント
- 基本料金は「契約容量」に応じた固定費で、電気を使わなくてもかかる
- 基本料金0円プランは使った分だけ支払う仕組み。
→ただし、調整費や単価が割高だったり、条件付きのプランもあるため要注意大切なのは「なんとなく」ではなく、「仕組みを理解して選ぶ」こと
【2025年最新版】電気代がまた値上げ…今後どうなる?



執筆者
小売電気アドバイザー
大山 泰正
小売電気アドバイザーの資格を持ち、電気の比較・情報サイト「エネべる」を運営しています。運営会社である株式会社enebellの代表取締役として、電力業界の最新情報や節約術に関する豊富な知識を提供。電力自由化や最適な電力プラン選びに関するアドバイスを分かりやすく解説しています。